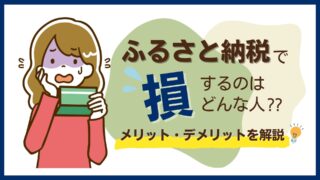歯止めがかからない日本の人口減少。国立社会保障・人口問題研究所によると、2060年には8,674万人まで減少する見込みであり、社会保障などさまざまな面において大きな影響を与えると想定されています。
人口減少は社会保障のほか地方財政にも影響を与えます。生産年齢人口の減少が税収減につながり、インフラに関しても整備がままならない状況となっていくかもしれません。こうなると不動産にも大きな影響があるでしょう。郊外では空き家が増え、地価が下がっていく可能性もあります。
このような問題に対処するために、各地方自治体においては「コンパクトシティ構想」を掲げるケースが多くなってきています。ではいったい、この”コンパクトシティ”とは何なのでしょう?このコンパクトシティ構想は将来的には不動産価格に影響を1与える可能性があります。どのような影響が想定されるのでしょうか?
目次
「コンパクトシティ構想」とは?
まずは、「コンパクトシティ構想」について解説していきます。「コンパクトシティ構想」とは、都市の中心部に公共施設や商業施設、住宅などを集約し、住民の生活圏を一定範囲内にまとめることで人口が減少しても都市機能を維持できるような”コンパクトな街”を目指すといったものです。 コンパクトシティ構想では、基本的に自動車を使わない範囲内での生活を想定しています。住民の利便性向上や財政負担の軽減、行政の効率化以外でも、公共交通機関の利用を促進することで環境にも配慮したものになっています。
実際に先行するコンパクトシティの成功例

実際にコンパクトシティ化に取り組んだ事例としては、富山市や金沢市、青森市などがあります。ここでは、富山市の事例をみていきましょう! 富山市では、世帯当たりの乗用車保有台数が全国トップクラスであり、郊外に人口が拡散していたため、中心市街地の活性化と公共交通機関の整備が急務でした。なぜなら、今後の人口減を見据えた時に、高齢者のように乗用車利用が難しい世帯では不便な街となる恐れがあったためです。
そこで富山市では、公共交通を軸としたコンパクトな街づくりを進めました。JR富山港線の廃止に伴い、低コスト・低騒音で運行できる「富山ライトレール(LRT)=次世代型路面電車」を導入。さらにバリアフリー車両の導入することにより、高齢者や障害をもった方にも利用しやすくなっています。 また、中心地にはグランドプラザ(全天候型の多目的広場)を配置し、中心市街地の利便性を高め地域の活性化に繋げています。 この結果、住民のライフスタイルに変化をもたらしました。
エリアによっては賃貸需要や土地価格が大きく下がる可能性も!?
中心部への拠点集約が進むと、当然、エリアによっては賃貸需要や土地価格が大きく下落する可能性が出てきます。 例えば、中心部から外れた郊外では、住む人が減れば減るほど地価は下がる恐れが高くなっていきます。
そのため、各都市においてどのようなコンパクトシティ構想が描かれているのかを確認することが大変重要な行動になってきます。

アパート経営成功の鍵は、『エリアの精査』にあり!
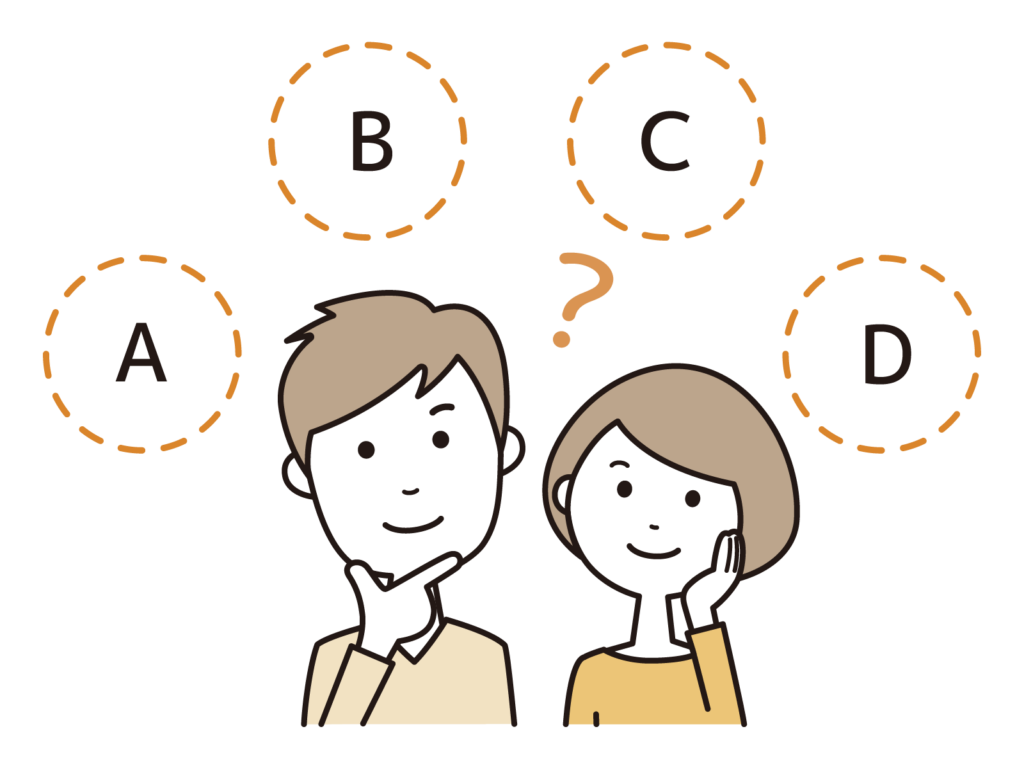
このように、コンパクトシティ構想は将来の街のあり方を大きく変える可能性が非常に高いと想像できます。中心部は活性化し、地価の上昇もしくは横ばいにつなげられる可能性もあるものの、郊外ではその逆の事態が発生するおそれがあります。
そのため、アパート経営を始める場合にはこれまで以上にエリアの精査をしっかりと行うことが非常に大切になってきます。先見の目を持ち、今後も住む街として機能する場所にターゲットを絞ることがポイントです。どの地域にどのような施設ができそうか、その構想は成功しそうか否か、自分なりのシミュレーションを行ってみるといいでしょう。
アパート経営をお考えの方は『土地がなくても、自己資金が少なくてもアパート経営はできる!!』をキャッチフレーズに土地から提案するアパート経営を紹介している
シノケンをオススメします。
シノケンでは無料の「ノウハウBOOK」もプレゼントしており、親切にアパート経営の仕組みから運用方法などを教えてくれます。

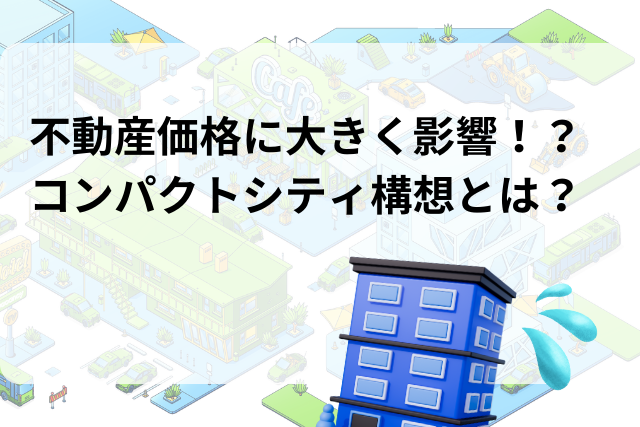
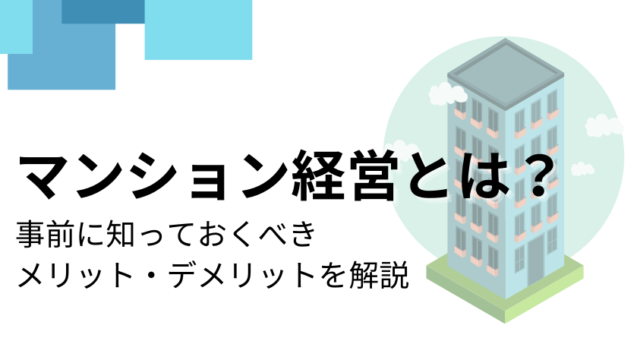
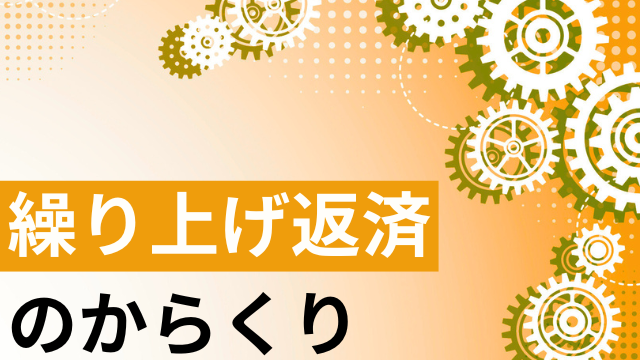
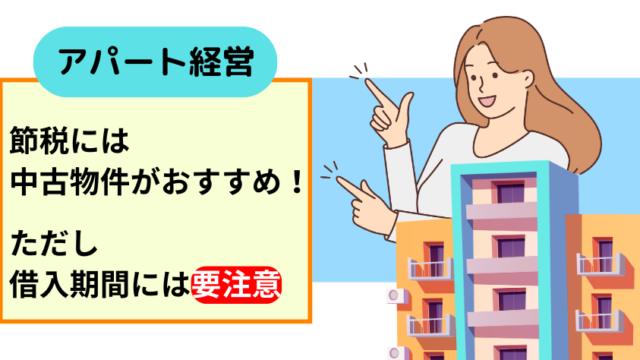
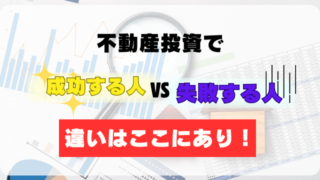
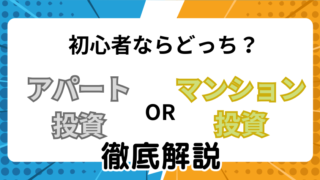
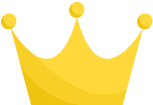 1位
1位 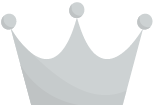 2位
2位 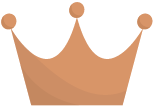 3位
3位